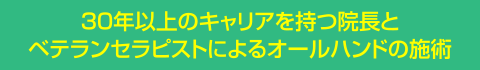横向きのマッサージ
側臥位のマッサージ
俯せの後、横向きの状態でマッサージを致します。
首の真横を斜めに走る胸鎖乳突筋を揉捏した後、目や頭に繋がる経穴を母指で押圧します。
次に首の後ろから肩にかけての肩甲挙筋や頸椎に沿って走る脊柱起立筋、盆の窪周辺の後頭下筋群を揉捏、後頸部の経穴を母指にて圧迫。再び側頸部を揉みほぐし、胸鎖乳突筋周辺の経穴をツボ押ししていきます。
肩から背中にかけての筋肉の緊張を揉捏でほぐし、上背部の経穴を母指で揉み押しして、デスクワークなどの負担がかかりやすい肩甲下筋や菱形筋などを揉捏でほぐしていきます。
次いで背中から腰にかけて揉捏と押圧でゆるめていきます。腸脛靭帯からスネの外側部分(前脛骨筋、腓骨筋等)をマッサージして内くるぶし周りや足の甲を通るの経穴を押圧いたします。
横向きの施術の後、仰臥位へと移行します。
首のマッサージ
側臥位での頸部の施術は側頸部を斜めに走る胸鎖乳突筋の揉捏から始めます。胸鎖乳突筋の停止部である側頭骨の乳様突起周辺から起始部の鎖骨近位部にかけて母指圧をかけ、左右に揺するようにして揉みほぐした後に天鼎(てんてい)という経穴をツボ押しします。次いで胸鎖乳突筋全体を母指にて押圧します。胸鎖乳突筋は、頚椎の屈曲に、回旋、側屈に関わる筋肉です。
前傾部の施術は胸鎖乳突筋の内縁に沿って頸動脈付近を弱圧で押圧します。この部位には人迎や水突といった胃経のツボが点在します。
後頚部の施術は肩甲挙筋のマッサージから始めます。肩を上げ下げする際の主力筋である肩甲挙筋は頭蓋骨と肩甲骨を繋いでいますので筋の沿って起始部から停止部へと揉捏で緩めた後、母指にて押圧します。
次いで頭蓋骨と背骨を繋ぐ頭板状筋の内縁を外側に向けて揉みほぐした後、母指にて押圧します。
首の上方から後頭部にかけては後頭下筋群を中心にマッサージいたします。後頭下筋群を構成する大後頭直筋、小後頭直筋、上頭斜筋、下頭斜筋を揉捏と押圧によって緩めていきます。
肩のマッサージ
肩の施術は肩甲挙筋の揉捏から始めます。この筋肉はうつ伏せの状態で揉みほぐすよりも側臥位の方がアプローチしやすく、母指圧を深部まで浸透させやすいので肩上部が凝り固まっている方には横向きの施術がお勧めです。
肩甲挙筋の前縁には肩井、胸鎖乳突筋の後縁には天鼎、肩の前方、鎖骨付近には缺盆というツボがあり、それぞれ母指にて押圧します。
次いで頚椎の側面と第1・2肋骨をつなぐを繋ぐ斜角筋に母指圧をかけ外側に向けて揉みほぐし、小腸経の肩中兪をツボ押しします。
次に肩甲骨内縁に沿って菱形筋の停止部を揉捏します。菱形筋は左右の肩甲骨同士を引き寄せたり、肩甲骨の下方回旋を行う筋肉です。
次いで菱形筋の深層に位置する上後鋸筋に母指で圧をかけ、揺するようにしてマッサージ致します。上後鋸筋は背骨と肋骨を繋いでいて、息を吸うときに肋骨を引き上げて呼吸の補助をする筋肉です。
背中の施術
横臥位での背中の施術は脊柱起立筋の一つである胸腸肋筋の揉捏から始めます。母指を内側の筋繊維に当て、外側に向けて捏ねていきます。
胸腸肋筋の延長上には腰腸肋筋という脊柱起立筋群の一つがあり、こちらも同様に揉捏していきます。この部位には神堂や魂門、陽綱等の膀胱経の経穴がズラリと並んでいますのでそれらを一つ一つツボ押ししていきます。
腰の施術
肋骨と腸骨を繋ぐ腰方形筋の後面、側面と多角的に揉捏し、この筋肉上にある肓門、志室等のツボを母指で押圧していきます。
次いで背骨に沿って走行する最長筋を背骨を圧迫しないよう、外側に向けて捏ねていきます。最長筋の腰部には三焦兪や腎兪等の背部兪穴が並びますので母指の先端を使って押圧します。
腰部多裂筋のマッサージ
多裂筋は首の後ろから腰にかけての深層を縦に走っている長い筋肉で背骨の横突起から一つ上の背骨の棘突起まで、背骨の一つ一つを繋いでいる細かい筋肉です。主な役割は体を反らす動きや上体を横へ傾ける動き、体を捻る動きですが、背部の奥のほうに位置していますので前傾姿勢の維持や細かい動きを微調整する筋肉でもあります。腰椎が後彎してしまっている方などはここが伸びた状態で固まっている傾向があります。
施術は側臥位のお客様に対して施術者は前方からアプローチします。一番から五番腰椎の棘突起と多裂筋の間に母指圧をかけ、外側方向へ向けて背骨から引きはがすようにしてリリースしていきます。
腰部起立筋ほぐし(上位腰椎周辺)
腰椎はL1からL5番まで、五つの骨から構成されていますが、下位腰椎の前弯が強く、その周囲の脊柱起立筋がこわばっている場合などに用いる施術法です。四番腰椎や五番腰椎が前方に大きく湾曲している方の多くは上位腰椎は骨の並びがフラットかもしくは後湾していることが多く、その分下位腰椎に負担がかかりやすい傾向があります。ここでは上位腰椎にアプローチすることで腰部全体のモビリティを誘導するような施術法をご紹介いたします。
側臥位のお客様に対して施術者は前方からアプローチします。まず、お客様の腰椎が前彎しないように前ももをブロックしておきます。片方の手で前彎が強くなっている下位腰椎の棘突起を押さえ、もう片方の手は胸郭に当てておきます。その状態からお客様には背中を反らしながらみぞおちの辺りを前に突き出すようにしていただき、同時に胸郭に当てた手で動きがスムーズになるように補助して上位腰椎を前彎させていきます。
この操作によって腰部脊柱起立筋がある程度緩んだ後に押圧や揉捏で腰部全体をもみほぐしていきます。
臀部のマッサージ/上殿神経からのアプローチ
中臀筋や小殿筋、大腿筋膜張筋など、臀部の外側が凝り固まっている方の多くは、梨状筋が硬くなることで上殿神経が圧迫を受けているケースがよくあります。その場合、臀部外側の個々の筋肉のマッサージに加えて梨状筋をほぐすことで上殿神経への圧迫を緩める施術法についてご説明いたします。
お客様には横向きで寝ていただき、施術者は背側からアプローチします。中臀筋はやや表層にあるのでそのままリリースしていきます。先ず、中臀筋の起始部である腸骨稜の下方に手根をあて、圧を大腿骨大転子の方向へ向けて上殿神経を絞扼からリリースしていきます。次いで中臀筋の停止部である大転子の上方部分に対して肘または指圧をかけ、リリースしていきます。小殿筋も同様に起始部と停止部からアプローチします。
次に梨状筋からのアプローチです。側臥位の状態で股関節を屈曲していくと梨状筋の位置が下がり梨状筋上溝が開いていきますのでそれを利用します。お客様の膝を上方へ上げていき、梨状筋上溝を広げていきながら前腕部を使って梨状筋を押し下げるようにして上殿神経をリリースしていきます。
前鋸筋+菱形筋のリリース
前鋸筋と菱形筋は肋骨部分で筋膜の連結があり、肩甲骨の外転、内転に関わっています。この二つの筋肉は拮抗筋といって相反する動作に携わります。前鋸筋が収縮すると肩甲骨は外方向へ動き、菱形筋が収縮すると肩甲骨は内方向へ動きます。
パソコン操作や車の運転などで腕を前に出している時は前鋸筋が収縮して肩甲骨は外方へ寄っています。当店に来られるお客様にもデスクワークや運転のお仕事をされている方々が多くいらっしゃいますが、そういった方々の大半は肩甲骨が外側へ寄っていて前鋸筋が縮んだ状態で固まっていて、菱形筋が常に伸ばされた状態になっていっます。
そのような場合は肩甲骨を内側へ動かすことで前鋸筋を伸張し、菱形筋を収縮させる運動操作を行います。この施術法は肩甲骨の左右への可動域が広がるのでゴルフや水泳などをされる方々にもご好評いただいています。
施術は横向きの状態で行います。施術者は後方からアプローチしてお客様の上になっている側の肘を後方へ誘導します。同時に肩甲骨の外側淵を内転方向へ押していきます。
この施術によって前鋸筋の伸張と菱形筋の収縮を同時に行い、肩甲骨を定位置へと誘導していきます。
小胸筋のリリース
小胸筋は胸にある小さな筋肉で胸(第3~第5肋骨の前側部分)から肩(肩甲骨の烏口突起という鎖骨下の出っ張り)にかけて斜めに走行しています。肩甲骨の下制(下方へ動かす)や下方回旋(右の肩甲骨を時計回りに、左の肩甲骨を反時計回りに動かす)、肩甲骨を前方へ引く動作などに関与しています。また、息を吸う際に胸郭を引き上げ、吸気の補助もしています。肩甲骨を外転させる役割もあるので肩甲骨が外方向へ流れていく動きを前から作っているのがこの筋肉です。なのでここがあんまり収縮していると肩が内巻きになって背中が丸まりやすくなってしまいます。
小胸筋は脇腹にある前鋸筋との連携も非常に強いのでこの二つの筋肉をセットでアプローチするようにています。
施術は側臥位のお客様に対して後方からアプローチします。上になっている側の前腕を把持して肩関節を外転及び伸展位で保持します。その状態で小胸筋の起始部から停止部に向けてゆっくりとストリッピング(滑らせるように摩るマッサージ)をかけていきます。肩関節の角度を変えながら繰り返し行っていきます。
次いでお客様の腕を軽度外転させた状態で四指を肋骨の丸みに沿って外側から大胸筋と小胸筋の間へ潜り込ませていきます。もう片方の手でお客様の肩を上方から抑え込み、肩を下方へ引いて潜り込ませている四指の上に被せるようにします。同時に四指で小胸筋を押圧してリリースしていきます。
次にお客様の脇の下から手を通して肩を前から抑え、もう片方の手で肩甲骨を包み込むようにして抑えます。その状態から肩甲骨の上角が下がるように上方回旋させます。その上で肩を後方へ倒すようにして肩甲骨を後傾させます。この操作を数回行った後、肩回しをするようにして動きの中で小胸筋をストレッチしていきます。
棘下筋上方繊維のマッサージ
棘下筋は肩甲骨の肩甲棘という隆起した部位の下にあり、肩甲骨の後面を広範囲に覆っています。ここでは手を後ろに回す際に制限となりやすい棘下筋上方繊維のリリース法をご紹介します。肩関節の内旋動作で棘下筋を伸張させながら徒手的に押圧を加えることでより筋肉を柔らかくしていきます。
| 施術法 |
| お客様には側臥位になっていただき、施術者は前方からアプローチします。お客様の上腕と前腕を固定した状態で四指で棘下筋上方繊維を捉えておきます。そこから肩関節の内旋を誘導しながら棘下筋上方繊維にあてている四指で肩甲骨の内側方向へ押圧することで棘下筋をほぐしていきます。 |
側臥位での肩甲挙筋のマッサージ
肩甲挙筋は僧帽筋上部線維と共に長時間のデスクワークや頭が前に出た姿勢によって負担になりやすい筋肉です。肩甲挙筋が硬くなると肩甲骨の内側を走行する肩甲背神経を絞扼して上背部の筋肉を萎縮させていることがあります。ここでは肩甲挙筋を短縮位でほぐすやり方をご紹介します。
| 施術法 |
| 側臥位の状態で肩甲骨を挙上し、腕を後ろに回した姿位にして肩甲骨を下方回旋とし、肩甲挙筋を緩めた姿位とします。そこから肩甲骨上角部位に付着する肩甲挙筋停止部付近を両手指で挟み込むようにして横断方向へ揺らして周囲組織との滑走性を出していきます。同じ要領で筋腹部分や起始部周辺迄施術していきます。 |
肩甲下筋のマッサージ
肩甲下筋はローテーターカフの一つで肩甲骨の裏側の肩甲下窩(凹面状に浅く窪んでいるところ)から始まり、上腕の前側にある上腕骨小結節に停止しています。この筋肉が収縮すると上腕骨を前側方向へ引き込む動作になり、腕の骨全体が内に向かって回旋する形になりますので肩関節の内旋動作になります。
施術は横向きの状態で下部繊維のマッサージから始めます。お客様の肩関節を水平内旋の姿位とし、肩甲骨の内側縁を把持します。もう片方の手で肩甲骨外側縁を内側へ向けて押し込んでいきます。そこから肩甲骨内側縁を持ち上げ、肩関節が内巻きになるように動かし、外側縁の母指圧を浸透させていきます。
次に肩甲骨内側縁から四指を潜らせるようにして肩甲骨と肋骨の隙間に入れていきます。その状態から肩甲下筋の起始部に四指圧をかけ、筋繊維を横断するように揉みほぐしていきます。
前鋸筋ほぐし
脇腹に広く分布する前鋸筋は肋骨の側面から始まっていて肋骨に沿うようにして後方へ走行し、肩甲骨の裏側へと潜り込み、肩甲骨の内側縁に停止します。肋骨に付着している起始部のところが鋸(のこぎり)のようにギザギザした形状であることから命名されているようです。この筋肉が縮むと肩甲骨が肋骨に沿って前方へ動かされますので肩が内巻きになって胸が縮んだ状態になります。パソコン操作などで手を前に出し、背中が丸まった姿勢を続けているとこの筋肉は収縮しています。デスクワークに従事する方々の大半はここが縮んだまま固まっていますのでここでは前鋸筋を伸張する施術法をご紹介いたします。
施術は側臥位のお客様に対して後方からアプローチします。上になっている側の腕を腰に回します。そうすることで上腕骨の重さが後方へかかってきますから肩甲骨を背骨側に動かしやすい環境が整います。その状態から肩甲骨の外側縁を手根で押さえ、内転方向へ落としていきます。この時、床面方向へ垂直に落とすのではなく、斜め上方向に角度をつけると本来の前鋸筋の走行と一致するので内転動作がしやすくなります。
次いで前腕部を前鋸筋の肋骨付着部分に軽く当て上下にゆっくりと摩るようにしてわき腹部分を広範囲にマッサージしていきます。
小殿筋ほぐし
小殿筋は股関節の外側(お尻の外側)深層にあるインナーマッスルで腸骨の殿筋面から始まり、下方向へ走行して大腿骨大転子の前面に停止しています。この筋肉が全体的に収縮すると股関節を外転(脚を開く動作)させ、前部繊維はもも上げの運動や脚を内側に捻る運動、後部線維は脚を後ろへ動かしたり、外側へ捻じる運動に携わります。また、小殿筋は骨盤を前傾させたり、後傾させたりもしますので、前部繊維があんまり硬くなってしまうと骨盤が前側に倒れすぎて腰の反りがきつくなったり、後部線維があんまり硬くなると骨盤が後ろへ傾いて腰が丸まってしまいます。
ここでは小殿筋を伸張させた後に全体の筋繊維を揉みほぐす手技をご紹介いたします。
施術は横向きの状態で行います。表層にある中臀筋を緩めておくために施術する側の股関節を外転位(脚を開いた状態)としておきます。片方の手で停止部である大腿骨大転子を固定し、もう片方の手で起始部に母指圧をかけ、小殿筋を大転子から引き離すように近位方向へ押していきます。
次に筋繊維の走行に対して横断するように起始部から停止部へと揉捏していきます。組織の表面が全体的に柔らかくなってきたら浪越圧点というツボを長めに押圧します。
肩関節骨頭へのアプローチ
肩関節の骨頭(肩甲骨にはまっている上腕骨の球体部分)を後方へ滑らせる操作法です。
腕を前から上へ上げる場合は骨頭は後方へ滑る必要があります。滑りづらくなる原因としてはローテーターカフ等の肩関節周囲筋や関節包などの影響が多いと考えられますが、ここでは関節包へのアプローチ法をご紹介いたします。
まずは単純な骨頭の後方への滑り操作を行い、ある程度、筋肉がほぐれてきたら肩関節屈曲動作で動く骨頭の起動を再現しながら腕の挙上動作を行っていきます。
始めにお客様には施術する側の肩を上にして側臥位になっていただき、施術者は後方からアプローチします。片方の手の水かき部分で肩関節の後部を固定します。もう片方の手の母指球と小指球の間に骨頭の小結節を挟み込みます。そこから肩甲骨の傾きを考慮して骨頭を後方へ滑らせていきます。
肩関節の周囲筋がほぐれてきたらお客様に仰向けになっていただき、施術者は頭方からアプローチします。肩関節屈曲時の骨頭の軌道としては関節窩に対してまず背側方向へ滑っていき、次いで尾側方向へ滑り、その後やや上方へと滑っていくのでその動きを再現するように上腕を把持して骨頭を動かしていきます。
胸腰筋膜へのアプローチ
胸腰筋膜は、胸椎や腰椎に付着する筋肉を覆っている非常に分厚い表層の組織で、仙骨から始まり、後頭骨や脊柱起立筋群の一番外側である腸肋筋の端につながっています。この筋膜はいろいろな筋肉と表層の膜組織レベルでの連結があります。運動的な特徴として有名なのは、大臀筋の張力が仙骨を介して反対側の胸腰筋膜に伝達されるという事です。これは対角方向への筋出力の伝播を可能にしているということです。わかりやすい例が歩く時や走る時に左脚を後ろへ運ぶと同時に右腕が後ろへ引かれるといった動作です。これは左の大臀筋から発せられた力が胸腰筋膜を介して右側の広背筋に伝わるためにスムーズに行われる運動です。もちろん、右脚と左腕を同時に後ろへ運ぶといった場合も同様に胸腰筋膜が関わっています。
また、この筋膜の中葉といわれる部分においては脊柱起立筋や腰方形筋、大腰筋といった腰部の筋肉同士が滑りやすくなるようにそれらを隔てているという役割もあります。なので胸腰筋膜の中葉の部分があんまり硬くなってしまうと腰部の筋肉同士の滑走がスムーズにいかなくなり、摩擦が多くなって腰の筋肉の負担も増えてしまいます。
なので硬くなった背筋を揉みほぐしてもなかなか柔らかくならない場合は胸腰筋膜からのアプローチも同時に行う必要があると考えられます。
施術は側臥位の状態からやや前方に体全体を傾けていただいた姿位で行います。胸腰筋膜の付着部である腰部腸肋筋に母指圧をかけ、腰椎の横突起の方向へ向けてマッサージ圧を浸透させながら上下、前後方向へ揉捏していきます。少しずつポイントをずらしながら繰り返し行っていきます。
次に側臥位の状態から上になっている側の脚を前に落とし、下になっている側の脚を大きく後ろへ引いた姿位をとっていただきます。その状態から片方の手で前側に落とした膝を押さえ、もう片方の手で同側の肩を押さえて腰をやや反らした状態で体幹を回旋させていき、胸腰筋膜を伸張していきます。
恥骨筋ほぐし
恥骨筋は内転筋群の中でも股関節の近くに存在して比較的ボリュームがあり、筋の走行も大腿骨の頸部と平行に位置しているので、股関節の安定に深く関与していると考えられます。また、もも上げ動作や開いた脚を閉じる動作、脚を外へねじる動作などにも携わっています。
ここでは反感抑制と等尺性収縮を使った恥骨筋のほぐし方をご紹介いたします。
まず、お客様には側臥位になっていただき、上になっている側の脚を天井方向へ持ち上げ、恥骨筋を股関節外転位で伸張しておきます。そこから持ち上げた脚を後方へ動かしながら足先を外側へと動かして股関節を伸展、内旋させて伸張していきます。
次に反感抑制によるリリース法です。施術者は片方の脚をお客様の寛骨にかませて骨盤を固定しておきます。施術する側の下肢を外転、屈曲、内旋の状態にします。その状態からお客様に下肢を持ち上げる前の状態に戻す動作をしていただき、恥骨筋を収縮させることで反感抑制によってリリースしていきます。
次に等尺性収縮を使ったほぐし方です。お客様には仰向けになっていただき、施術する側の膝を立て、外へと倒します。その状態で施術者は膝を固定しておき、お客様には軽めの力で膝を立てた状態に戻す動作を5秒ぐらいしていただきます。この動作を数回繰り返し行っていき、恥骨筋を緩めていきます。
大腿二頭筋ほぐし
大腿二頭筋はもも裏の大きい筋肉であるハムストリングスの外側頭にあたります。骨盤の坐骨結節から始まり、斜め下方・外方へと走行して膝裏外側のスジとなる筋肉で、大腿二頭筋の滑走性の低下は膝関節の伸展制限(膝を伸ばしきれない)とも関係があります。
また、膝関節を曲げていく際に膝裏の外側につまり感がある場合は大腿二頭筋の滑走がスムーズに行われていないことが考えられます。大腿二頭筋は膝の屈曲に伴って近位に滑走すると共に筋が持ち上がる動きが必要となってきますので、ここではその動きを誘導する施術法をご紹介します。
お客様には施術する側の脚が上になるように側臥位になっていただき、施術者は側部の方からアプローチします。
お客様の膝関節を軽度屈曲させ、施術者の下肢にのせて、両手で大腿二頭筋を摘まみ上げるように把持しておきます。そこから自働により膝の屈曲動作を行っていただきます。その動きに合わせて大腿二頭筋を持ち上げ、近位方向へ誘導していきます。
適宜、ポイントをずらしながら、大腿二頭筋がほぐれるまで繰り返し行っていきます。
当店は藤沢駅南口徒歩2分
JR東海道線、小田急江ノ島線、江ノ島線の3路線から楽々アクセス。ドン・キホーテ藤沢駅南口店から歩いてすぐ、ハウスメイトショップ藤沢店の上、4階です。
ご予約はお電話でお願いいたします。
Tel.0466-28-5086
【営業時間】
平日 13:00~22:00(ご予約受付時間 12:00~21:00)
土日祝日11:00~22:00(ご予約受付時間 10:00~21:00)
神奈川県藤沢市南藤沢にあるマッサージ店です。このページでは、横向きの状態での施術内容をご紹介しています。